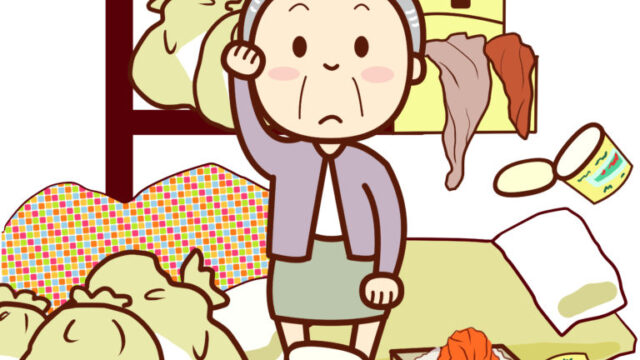高齢の親の独居生活を円滑にするアイテムの紹介です。
親も高齢になると、物忘れが出てきたり、特に買い替えた物の使い方が理解できなかったりしがちです。その度に「これはどうしたらいいんや?」という度々の電話にイラっとし、説明してもその場限りで、また同じ質問が来ます。更にイラっとする悪循環が我が家でも日常でした。
せっかく親のために買った物も、「わからんし使ってない」と言う始末。私が居なくても、見たらわかるように手書きの説明書を何度書いたことか・・・
手書きの説明書も見るのは始めだけ。一人で見て理解することよりも、聞いてすぐ答えてくれて、追加でどんな聞き方をしても答えてくれる娘の方が便利というわけです。
そして何度も同じ説明に追われる私が怒ると、もうその物やその機能を使わないという手段をとるのです。
そこで、思いついたのが、単純な『視覚的表示』です。いろいろな「シール」を駆使することで、直感
的に動作を誘導できる優れた方法なので、お困りの方はぜひ試してみて下さい。

超活用アイテム
その1 100均の丸形シール
これは活用度無限とも言える神アイテムです。直径が5mm、1cm、1.5cmといったサイズ展開があり、使う箇所で選べるのが便利です。通常の紙のカラーシールもありますが、マスキングテープの材質もあり、用途に応じ使い分けしています。
その2 100均のマスキングテープ(ラベル型デザイン)
これは、クリアファイル毎に整理した書類のラベルとして活用したり、スマホや家電などで文字を書き込みたい時に活用しています。
その3 テプラ
わざわざ買うとなると、マスキングテープで代用してもよいですが、我が家のように忘れ去られた遺物になっているテプラがあるなら、今すぐ復活させましょう。
我が家での活用例
スティック型掃除機
特にゴミ捨ての時や、使い方によってはずすパーツ部分に使用。連結部分に同じ色の丸シールをそれぞれ貼り、はずして元に戻す時に色を合わせることで、繋げる箇所がわかります。
IHコンロ
ガスからIHに変えた際に、ボタンが沢山で混乱。普段の使い方を聞いた上で、使うボタンだけ、コンロやグリル別で丸シールの色を変えて、操作順に番号を書くことで、戸惑うことなく操作できています。
洗濯機
買い替えたら、操作がわからず混乱。これも普段の使い方を聞いて、使う機能に沿って丸シールに操作手順の番号を書いて貼ったことで、その番号だけ見て使えています。
音楽プレーヤー(MP3)
小さし丸マステシールに音量「大」「小」「★」など付けたり、電源に目印のマステシールを貼ることで、何とか使えています。画面で予期せぬことになればお手上げですが。
スマホ
持ち方のクセで、スマホを持った時に指の位置が丁度音量ボタンや電源ボタンを抑えてしまうらしく、ずっと不満を言っていたのですが、指位置に目印マステシールを貼ると、どこを持つと差し障りが無いのかがわかり、とても喜ばれました。
また、マナーモードがなかなか覚えられず、スマホの裏にマステラベルシールに「マナーモードは赤」と書いて貼ることで、本人にわかるようになりました。
家の電気スイッチ
テプラが大活躍。トイレや台所、洗面所、お風呂など、電気のスイッチがあり、なおかつ2つ3つ並列していると、そのうちどれがどれやらになると思い、まぎらわしいスイッチに全てテプラで「洗面所」など、何のスイッチかを表示して、さらに場所によって色シールも付けると、劇的にわかりやすく便利になったようで、実家に行く度に喜ばれています。
書類の整理
介護保険、医療保険、ガス電気・・・様々な書類は気づけばどんどん溜まっていきます。クリアファイル別に入れて整理し、マステラベルシールに項目を書いて貼っておくことで、いつでも必要な時に確認しやすくなります。
トイレ
スイッチにはテプラで「トイレ」と表示することで格段にわかりやすくなりましたが、更にドアにトイレマークを付けました。もし認知症になっていき、トイレの場所がわからなくなって間に合わなくなる危険性を想定しています。インターネットの無料画像を印刷したもので、本人が嫌がったら剥がせるように簡易的に貼りましたが、思いのほか受け入れてます。
戸締り火の元確認
外出時の確認事項を広告の裏に書いて玄関の内側の目につくところに貼っています。わざと手書きで書いています。活字だと興味の無い内容には反応薄くなりがちなため、目に留まりやすい手書き文字にしました。毎日ちゃんと見て確認していると自己申告がありました。
コロナ過以降、人を家に招くことが無くなり、その分、人目を気にする親も、自由にシールや貼り紙をしても何も言われることも無く、返って感謝されている感じです。
高齢の独居は、本人が一番不安なことも多く、気づかない間にできないことが増えていきます。シールや貼り紙をすることで、パッと見てすぐ安心して自分で行動ができる基盤を家族が一緒に作ることで、独居でも安心した生活を続けていくことに繋がっています。