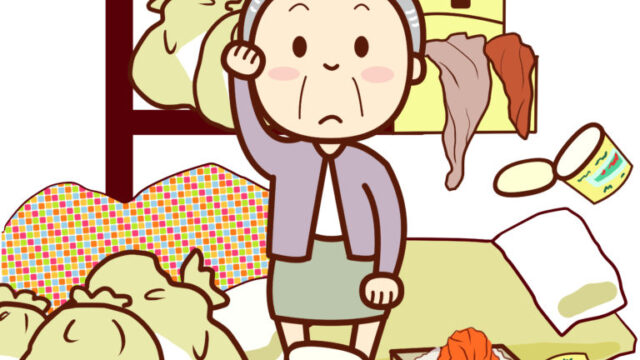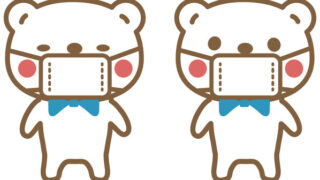親が認知症にならないために、どんなことができるだろうと焦りを感じつつ、思いつく度に行動に移していましたが、思いとは裏腹に逆効果になることもあるというお話しです。
「助ける」といっても、いろいろな助け方があります。まず、これだけはという項目を挙げてみました。内容は、家や親によって変わってきますが、私が必要だと感じて、やっておいて安心したものです。参考になればと思います。
独居生活を持続するために必須項目
住まいの使い勝手
ガスコンロからIHコンロへチェンジ
独居なので、火の元が一番心配するところです。使い方がわからないと言いそうでしたが、思い立ったら早めに買い替えないと、歳をとるほど、現時点よりも覚えが悪くなります。本人がよく調理する使い方を聞いて、わからない操作は、手順をシールで示すことでクリアしました。
ケガ防止策
生活動線内で、ケガにつながりそうな段差や空間に、予防策を施します。これも家によって危険個所は様々なので、ケガする前に見つけて対処しておいた方が良いです。
私の実家の場合は、ベランダに出る時に大きくまたがないと出られないのですが、結構な高さで、普通に私でも引っかかってコケそうになるので、手すり付き階段(3段くらい)を部屋側に置いて、低い段差でベランダへ出られるようにしました。ステップだけより手すり付きの方が安全で良かったです。
また、1階に掃き出し窓外に奥行きの狭い洗濯物を干せるスペースがあるのですが、床が部屋の延長線上では無く、地面が40cmほど下にある溝状態。上ばかり見てると落ちるという危険ゾーン。そのため、部屋とバリアフリーになるように丁度良いサイズのベンチ椅子を探して購入。なかなか幅と高さと奥行きが一致する物が無くて、最後の手段はDIYと思っていた矢先に発見!そのベンチを設置することで、落ちずに安心して干せるようにしました。
セキュリティ
窓・・・大きな窓には飛散防止シートを貼り、防犯ロックをしています。この防犯ロックもまた、いろいろな種類がありますが、施錠を自分で開けられないのでは?という一抹の不安があったので、簡単な仕組みのタイプを購入しました。大きな音が鳴るものだと、それはそれでびっくりしてパニックになるかもしれないので音系は回避。
また、玄関横の小窓には、家の中が丸見えにならないようにホームセンターで売っている窓の目隠し用のアイテムを施しています。プラスチックの薄い板を格子ごとに張り付けるため、風は隙間から通り、半透明なので光も遮らず、風通し、採光に問題無しで良いアイテムです。
玄関・ベランダ・・・防犯カメラを設置。取り急ぎダミーを設置しましたが、様子を見て本物も検討してもいいかと思っています。また、インターホンにはセールスお断りのプレートを貼っています。これはもう何年も前にしたのですが、当初から効果あって、セールスが来なくなりました。
電話・・・固定電話は、防犯アナウンスや非表示をブロックする電話に買い替えて、電話口に出る前に怪しい電話がつながらないようにしました。携帯電話は、電話帳アプリを入れましたが、これはまだ今ひとつ効果の実感がないです。
うっかり忘れ防止
出かける時の点検項目を玄関に出るところに貼り紙をして、火の元、電気など確認しから出かけるようにすることで、本人も確認事項を可視化できる安心感があり感謝されています。
独居生活を円滑にするための項目
住まいの整理、整頓、片付け
私の親は元々整理整頓ができる人だったので、部屋は散らかってはいないものの、先の手間(遺品整理)を考えて、もう着ない衣類や使わない物を断捨離するようにしました。意外に多く、早めに着手してよかったと思っています。今後、介護に必要な物を用意するスペースもできました。
使えないで終わらせない
これは高齢者あるあるで、家電が壊れたりして新しく買い替えたりすると、使い方がわからなくなって困るケースです。困った末に掃除ができない、洗濯できない、料理できない、そうなると、生活が乱れていきます。
解決策として、使い方をマスターするために手順シールや、単純明快に書かれた取扱説明書を用意します。最初に手間がかかりますが、一人で使えることが目的なので、自立した生活を送ってもらうための手段です。
親の独居は、助ける加減が難しい
独居するにあたって、何でもかんでも助けると、親は子に依存していき、その結果、独居なのに自分で何もしなくなるという本末転倒の事態になります。認知症へまっしぐらコースです。私の親も途中からグンと依存度がアップしたため、加減を考えるようになりました。
助けすぎは依存を招き、放置しすぎは、介護する側にとっても準備できなかったり、気づかないうちに認知症が進んでいたり、加減は難しいものです。

できることを奪わない
助けすぎないということは、時間がかかっても、何とか一人で本人ができていることを、大変という親切心で代わりにやってしまわないということです。
例えばどんなことが考えられるでしょう。どの手助けにおいても、全てダメなのでは無く、時には必要な場合もあります。状況を見て判断することがとても大切になります。
・買い物を代行すると、自分で考えて買い物をしたり、お金の支払いができなくなっていきます。重い荷物、体調が悪いなど、状況によって手助けしましょう。
・自分で行ける所に車で連れて行ってあげるのは、親切なようで、目的地まで自力で行けなくしてしまうことにつながります。歩いたり、交通機関を使ったりは足腰や脳を使うので、自分の用事であれば、自分で行けることが理想です。
・郵便物や大切な書類など内容確認の必要なものを、親が見ないからと子が確認を引き受けると、自分で読んで理解することをしないため、著しく理解力や判断力が落ちていきます。
・着替えや食事の時に早く済ませたい一心で過度な介助を行うと残存能力が失われる
高齢になると、できることが徐々にできなくなっていきます。助ける加減も、歳とともに日によって変化するものと意識して、その日の親の状況や状態を優先させていきましょう。
親の気持ち、子の気持ち
親は、いつまでも親という思いがあり、親だからまだ子や孫に自分がいろいろしてあげたいという気持ちがあります。
私は、これまで助けてもらって来た親に対しての親孝行、これからは、自分が助ける番という気持ちがあります。
この1~2年で、そんな親子それぞれの気持ちのバランスが崩れる時がやって来て、初めて親の高齢を受け入れていくようになったような気がします。
親の親である気持ちが、いつの日か、子に依存していく比重が増えて来て、今では関わるほどに、結構な依存体質に変化して来ました。
助けすぎによる依存なのか、考えること、理解すること、判断すること、それらを手放しにかかっているような、逆に言うと、やりたいことだけする、聞きたいことだけ聞く、めんどうなことは一切しないといった具合に仕上がってます。
付かず離れずの関係
独居というものは人によって、とてつもなく寂しい毎日。私の親もまた、昔からお喋り好きで賑やかが好きで、アクティブなタイプだったので、今の生活は「気楽だけど寂しい」と言っています。
今はまだ親の喋り相手は存命で、何人か居てくれているので助かりますが、周りと話しができなくなってしまうのもそう遠くない未来です。
親が周りや社会と交流できている今、私が親の喋り相手になってしまうと、自分のことばかり話す友達(←お互い様)よりも、気分良く時間無制限的に話し続けられ、困りごとも解決してもらえるため、現在の周りとの関係を薄くしてしまうことがわかりました。
そんな親の依存体質を戻すために、付かず離れずの関係を取るようにしたところ、私から連絡しない限りは殆ど連絡は無く、近所の体操だ、お友達とランチだ、スポーツジムだ、暇な時は図書館行ったりと、常に予定を入れている様子。
結論
いつでも助けられる体制でいて、それ以外は付かず離れずの関係を保つことが、親の独居生活を少しでも長く続けられるコツです。