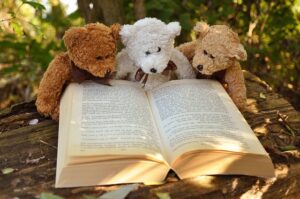認知症高齢者にとって誰かと会話する機会は脳の活性化の点でも大切なこと。今回は認知症高齢者のコミュニケーションのお話しです。
会話をするレベルは人により様々で、会話のキャッチボールがしっかりできる人も居れば、話せても聞くことや理解が難しい人、その逆で相手の言葉を理解できるが返答となると難しい人、脈絡のない言葉を並べる人、反応が薄い人、実に個人差があります。
どのようなレベルであっても、毎日の生活の中で人と関わりをもつことは本人にとって刺激になるので、話しかけることや、言葉として理解できなくても耳を傾けることに意味があります。
理解をしようと素直に聞く人は多い
お話し好きのおばあさんは、いつも社交的で周りの人に積極的に話しかけています。しかしながら数年前に比べるとどんどんその内容は意味不明になり、話しかけられた側が困っている様子をよく見かけるようになりました。
「お母さん何歳?私2歳!(←本人は面白い冗談のつもり)」急に始まるこの展開に誰しもが戸惑います。そして「2歳の子が居てたらいいね」と。なぜいつも2歳なのか、本人はそのやりとりに夢中のため真意は不明のまま。
他にも「あなたカッコイイ~」「なんでそんなにかわいいの?」と見る人会う度お世辞を言いまくるため、お世辞とわかる人にはウンザリされ、お世辞とわからない人には高齢になって同じ高齢の人から言われる言葉に困惑気味という、いったいどっちが気の毒なのか。
自分で聞いておきながら、相手が質問の意味がわからず聞き返すと「もうそういうことでいいやん、わかったから」と自己完結。おそらく自分で振った質問だけど、内容は支離滅裂で自分でもわからず、それを認めることもできず、相手の理解力不足として強制終了する荒業。
そんなおばあさんに「何言ってるの?」と不快を表に出す人は少なく、意外と周りはみんな、一生懸命そのおばあさんの話に応えようとしています。認知症になって話す人も減り、誰かと会話できることを無意識に喜んでいるのか、認知症になっても大人の対応をしているだけなのか、おばあさんのフレンドリーさが心地良いのか、とりあえず拒否されない限り、職員は会話の補助に入っています。
認知症に思えないけど、やっぱりガッツリ認知症
どんなに的確な言葉を話したり、理解して返答したりしていても、しばらく話していると出て来ます。
雨がザーザー降りなのに「もうすぐ(雨が)やみそうやね」と。こういう時は「しばらくやみそうにないですよ」と返すのは無く、「そうですね、早くやむといいですね」と返すのがベスト。どんな時も真実を正すことが正解ではないです。
また、話の流れで、こちらから質問をしてみても、まるで振り出しに戻ったように同じ話が繰り返されます。何週もすると返す言葉が同じ場合もあれば、いろいろなレパートリーで返すこともあり、その時の自分の状態で返します。
認知症の人が話す内容に誤りがあることも、同じ話を繰り返すことはしょっちゅうです。その言葉に乗っかって話を合わせたり調整することで、認知症の人にとって話しやすい環境が生まれます。
聞こえないフリをするのは、やはりよくありませんので、もう嫌だ~となる前に、言葉遊びのように、いかに自分が楽しめる返し方をするかでウンザリする気持ちを乗り切るのも1つの手です。
会話は言葉だけでなく、表情やしぐさでも理解できるもの
言葉の理解ができているのか、理解はできないけれどこちらの言葉に応えてくれようとしているのか、言葉以外でもじゅうぶんコミュニケーションが取れることは多いです。
うんうんと首を縦に振ると、オッケー。反応が無いとイヤなのかもしれない。
表情が力が入らずリラックスしていると不快では無い。しかめっ面や眉間にシワが寄っていると明らかに嫌悪している。
手を持つとスッとまかせてくれる。拒否の時は漬物石のように重く、嫌なのか怖いのかで抵抗している。
言葉として一切発せられなくても、そうした表情やしぐさで読み取れる感情は多いです。
脈絡が無いけど何か話してる
日本語としては文脈が崩壊して、もはや音の羅列という人もいます。ただ、聴いていると、たまに理解できる単語や言葉が混じります。
そんな時は、すかさずその言葉を復唱します。「あ~○○ね!」
何を言っているのか全くわからなくても、表情がにこやかなら、楽しい話しなのだろうと、それに合わせて相づちを打ちます。怒っている表情で話していたら「それは大変でしたね」「困ったものですね」など不快に同調した相づちをうちます。
他にも「確かに!」「ホントですね!」「なるほど!」「へぇ~そうなんですね」「知らなかったです~」「え?わからない、どういうこと?教えて!」
まったく何を言っているのか、わからなくとも相づちを中心に会話をします。
その時の表情やしぐさを見ながら相づちをすることで、満足したり落ち着いたりしていき、会話を終えることができます。
反応が薄かったり無反応
何も話さない、話せない人に対しては、こちらがその時々で自由に話します。
「今日はもう〇月〇日なんですよ。あっという間に○○ですね」
「今日は過ごしやすいですが、これから季節はどんどん暑くなりますのでお身体気を付けてくださいね」「水分摂ってますか?水分大事なので細目に摂ってくださいね」
「夜眠れていますか?」
日にちや季節、天気や地元の情報を話すことで、見当識障害で日にちや時間や自分の居る場所がわからなくなっている人には、思い出したり、認識してもらいやすくしています。
他にも、体調のことや、介護をする者とされる者という気持ちの壁を崩すために、私自身のグダグダさが伝わる自虐ネタを話していることもあります。「○○さん、夜は眠れてますか?寝ても寝ても眠いのは私だけ~?」「私ずっと膝痛いんですけど、○○さんは大丈夫ですか?」といった感じです。
認知症高齢者のコミュニケーションはザックリおおらかが一番
認知症高齢者の人同士のコミュニケーションも、介護者とのコミュニケーションも、言葉尻を正確に捉えるとズレが生じます。そもそも言いたいことが言えない、理解できない状態が出てきているのですから、言葉はヒントとして考える方が上手くいきます。
もちろん言葉そのものが伝えたいことである場合もありますので、言葉プラスその時の状況と本人の表情やしぐさを含めて大きな視点で見ることで、一番近い感情を受け取ることができると考えます。
こちらから伝える時は、時に正確に、時に状況に合わせて、時にテキトーに、相手と直接関わりながら変化させてコミュニケーションをとっていくのですが、案外みんなザックリしていても簡単な言葉で話すからなのか、受け止めてくれています。